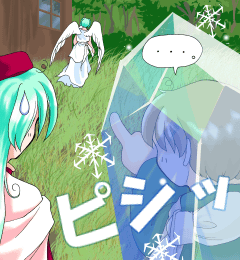|
がんばれ吟遊詩人! 〜ラヴェル君の場合〜
第十三話:精神世界(前編)
風の音がする。サワサワと葉の擦れる音も聞こえる。小鳥の鳴き声も。
「うーん……」
ぼんやりとラヴェルは目を開けた。木漏れ日が顔に当たる。
「ここは……?」
見回すとここは森の中。景色に見覚えはない。
辺りを見回しても自分以外に人がいる様子もなく、聞こえるのは風と小鳥の声だけ。
「生きてる……」
もう一度辺りを見回す。まだ午前中のような優しい日の光。木々の葉は春のようにみず
みずしく、柔らかい。もちろん足元の草も。
ラヴェルは足下に何かが光っているをみつけた。
手にとって見れば、途中で切れた皮紐の先に砕けたクリスタルのかけらが辛うじて繋がっている。それは付け根部分しか残っていなく、とても小さい。
重く思考の回らない頭から、その輝きが記憶を引き出した。
「レヴィン……?」
青い影は……やはり見当たらなかった。
「これはレヴィンの……?」
手に取るとその欠片はひんやりとしていた。だが、人に触れているような何とも言えない温かさも兼ねていた。
青黒い闇の中にふっと目を閉じて倒れて行く何かが脳の中を横切る。
頭を振ってそれを追い払うと、ラヴェルは拾ったクリスタルの欠片をポケットにしまいこんで立ち上がった。
一年にも満たない道中を思い出しながら歩き出せば、散々言われた嫌味や冷笑、からかいの言葉が幾つも思い出される。
だがどことなく惹かれるものもあった。
ラヴェルの知らない世界、未知の言葉、古い歌、そして……古の魔法、禁断の呪文。
見物でもしているかのようにラヴェルをそばで眺めていた赤い瞳も、旅に痛んだ青い衣服の影ももう横にはない。
旅立ちにクヤンから受けた忠告と、道中でレヴィンが話した言葉が絡み合い、ラヴェルの思考を更に迷路へと引きずり込む。
『俺が知るか』
『まったく、俺が何をしたというんだ』
思わず呟いた言葉は恐らく本音だったであろう。
しかし、本当にそんなわずかな言葉で全てだったのだろうか?
レヴィンは何一つ感情を表にしなかった。
もちろん戦いにいらついたような雰囲気はあったが、クヤンに追われ、魔物と断じられ、傷つけられても、一言も心情は吐き出さなかった。
剣に貫かれ、倒れ伏した時も無言のままだった。
悲鳴や呻き声すら上げなかったのだ。
その心中は誰にもわからない。
ぼんやりとした頭で見知らぬ森の道を進んでいると、木々の向こうで誰かが手を振っているのが見えた。頭の上で両の手を大きく振っている。
その姿にははっきりと見覚えがあった。亜麻色の髪、丸い顔、くすんだ緑色の、ふかふかしたコットンのローブ。
「おーい、おーい!」
「……王子?」
はっとする。
そうだ、確かさっきまでクレイルと共にいたはずだ。
二人して暗い神殿の奥で、とてつもなく恐ろしいものを見てきたのだ。
「ク、クレイル王子!?」
|
思い出して駆けつければ、それはやはり自国の王子であった。
「やあ、何とか死なずに済んだね。もっとも変なとこに飛ばされちゃったけど……」
「一体何が起きたんです? それに……ここは?」
そろりそろりと歩を進めていけば、やがて小さな村にたどり着いた。いまいち現実感がない。
まるで夢の中を歩いているように足元がふわふわする。
「うーん、こりゃ何かに巻き込まれたね。何だろ? 意識が……」
クレイルは考え込むように指先を頭に当てた。
「何だろうね、意識の流れみたいのが渦巻いてる。景色も感覚も現実感がないし、これはひょっとすると……」
森の中に開けている小さな村は、村というよりも集落といった感じで、穏やかな空気に包まれている。
クレイルが辺りを眺めている間、ラヴェルは疲れたように草の上にしゃがみこんでいた。
手持ち無沙汰に、猫じゃらしの葉っぱをぶちっと引き抜く。
「……あれ?」
確かに葉っぱは引きちぎれた。手の上にちぎれた葉が乗っている。
しかし、感覚がない。
ぶちっという音もした気がするが、良く考えてみると、したような気はするがしていないような気もする。
「はは〜ん」
それに気付いたクレイルが声を上げた。
「ラヴェル、葉っぱを引きちぎったと思ったでしょ。そう思ったから、そう感じただけ。実際には君は何も手にしていない」
「え?」
いわれて良く手を見れば、確かに何も持っていない。
しかし確かに葉っぱをちぎるという行為はしたのだ。実際手のひらに葉が……。
そう思って手を見ると、今度は手のひらにちぎれた葉っぱが乗っている。
「ラヴェル、ここはどうやら幻の世界だね。幻といっても、本当に何もないわけじゃない。意識の流れみたいのが作り出してるんだ。つまりここは誰かの記憶が作り出している幻影か夢の中……」
「じゃぁ、それってもしかして……」
ラヴェルは先程ポケットに忍ばせたものに手をやった。
ひんやりとした感触が指先に触れる。
しかし、これはどうしてここにあったのだろう。
いくばくかの疑問は感じたが、その疑問はとりあえず封じ、ラヴェルは先程の言葉を続けた。
「じゃぁ、ここってレヴィンの意識の中ってことですか?」
意識というよりは、心、あるいは思い出の中と言った方が正しいかもしれない。
「うーん、そうかもね。あるいはその記憶の中? 断定はできないけど、そんなところだろうね」
意識、記憶、心。
唐突にラヴェルの脳裏にレヴィンの声が響いた。
『明けと宵とを彷徨いし、流れゆく全ての魂魄(たましい)よ……』
気付けばその呪文の言葉をラヴェルも口に出していた。
「我が内に秘められしもの、目覚むれば淡く揺らめく炎となりて、共に永久(とわ)の時を巡らん……」
黒い鎧の騎士が崩れ落ちる。
かと思えば、レヴィンの姿が黒い霧のようになり、何かの魔法に焼かれて塵と消え去る。
どこかで見たような景色が、言葉と共に浮かび揺れている。
「ラヴェル??」
いぶかしむようなクレイルの声に、はっとしてラヴェルは口をつぐんだ。
「どうしたんだい? 謎解きみたいなことを口走って」
「え? あ、ええと……」
ラヴェルはもごもごと口ごもったが、やがてため息をついた。
「何だか急にレヴィンの声がしたような気がして……魔法の詠唱が……」
「ふーん?」
どこかで羊の鳴く声がする。
「ねぇラヴェル、僕の叔母上が巫女をやっていて精霊使いなんだけどね、世界は霊気とかエレメントとか、意思の流れみたいのが巡っているんだって。人間の魂や精霊もその流れが形をとったものだっていうんだ。ここはその意思の流れの中なんじゃないかな。多分レヴィンが倒れたときに、その流れの中に何かの拍子に放りこまれたんじゃないかなぁ」
その村はごくごくありふれた田舎の村だった。子供が老人に相手をしてもらって遊んでいる。
これはレヴィンの記憶にある風景の一部なのだろうか。
「……だとしたら普段のレヴィンからは想像つかない程、のどかな所ですね、ここ」
「そうだねぇ」
め〜〜。
足の生えた綿の塊が草を食べている。
太陽の光が心地よい。
「……のどか過ぎません?」
「……そう思う」
田舎としかいいようのない自分達の故郷を棚上げし、二人はしばし呆然とその様子を眺めていた。
「ところでラヴェル、ここってどこの思い出なんだろう?? レヴィンの故郷とかかな」
「え?」
唐突に話しかけられ、ラヴェルは一瞬言葉が出なかったが、やがて目一杯の疑問を問い返した。
「それって……ここ、アスガルドってことですか?」
「は?」
今度はクレイルの言葉が途切れた。
説明するようにラヴェルは付け足す。
「彼、天空人なんですよ」
今度こそ口をぱっかりと開け、クレイルはラヴェルをまじまじと見つめた。
「……ウソだろ?」
「だって、そう言ってましたよ」
聞き返されてラヴェルは困ったが、それ以上に困ったような顔をしてクレイルは村の向こうを指差した。
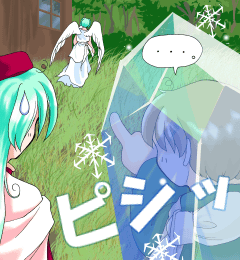
「おいおい、天空人ってのはああいうのを言うんじゃ…………え?」
自分で指差しておいてクレイルは目を疑ったようだ。
彼の指差した先には、背中に一対の翼を持った人間が地面すれすれにほとんど歩くように飛んでいった。
………………。
二人はぎぎぎ、と油の切れた扉のように顔を見合わせた。
「あ、あれって……」
「天空人、ですよね……」
それを追うと、一軒の家の前でふっと消えた。
試しに二人はそっとその家に近づき、中を覗いてみることにした。
|
若い男性が赤子をあやしている。
傍らのベッドには疲れたように女性が休んでいる。その枕元に立てかけてあるのは……竪琴だ。
室内には無邪気な赤子の声が響いているが、大人達の空気は重かった。
「その御子はな……」
窓の外からそっと覗くと、夫妻と赤子の他に、数人の司祭がいるようだった。重々しい声がどことなく憂鬱そうに聞こえる。
「その御子は多分……」
司祭の一人が窓辺に近づき、空を見上げた。
ラヴェル達は覗き見していたのがばれないように慌てて茂みに飛び込んだが、司祭の視線に釣られるようにして空を見上げ……絶句した。
空に幾つも島が浮かんでいる。
(島が浮かんでる!?)
唖然とするラヴェルの横で、クレイルも同じような顔で空を見上げていた。
(なっなっなっ……あアあスガルド〜!?)
やはりここは天空界なのだろうか。
空を見上げる二人に、司祭の憂鬱そうな声が再び聞こえてくる。
「その御子は恐らく、上都のセラ達の子供だ。上都は遥か昔に滅びたと聞くが生き残りでもおったのだろう。その子供は、セラの生まれ変わりだ。身体こそお前達の子供、人間。だが、その宿す魂は貴き精霊のもの」
驚き、恐怖の色すら浮かべて夫妻は顔を見合わせた。
「そんな、セラといえば古くからの神秘的な方々、それがなぜ私達のところへなど生まれてくるのです?」
「わからぬ。セラ達は天使にも匹敵するほどの精霊、秘められた能力は計り知れぬ」
セラフ。
ラヴェル達、下界の人間にとっては、すでに伝説でしかお目にかかれない、古い種族。
緩やかな衣をまとい、背に一対の白い翼を持った美しく神秘的な姿をしているとされ、また、魔法にも長けていて、古代魔法と呼ばれるものを編み出したのもセラ達だとされている。
その美しい姿がラヴェル達下界の人間が持つ、天空人の一般的なイメージであった。
目の前の家の中にいる人間達は、取りあえず普通の人間だった。地上の人間達と変わらない。
しかし見上げれば空に島が浮かんでいる。
(ここは……天空? アスガルドの下の島なのかな……?)
司祭の声が憂鬱さを増した。
「なればこそ、だ。その子は魔物に目を付けられている。魔物がセラの魂を狙っておる」
「!」
家の中の空気が凍った。別の司祭が話を引き継いだ。
「二年じゃ。その子が二歳になった時、魔を崇める者たちはその子を我が物にして去って行くだろう」
「セラともなればその能力は魔物にとって見れば垂涎の的。十四歳にもなればその器に魔物を移し入れられ、やがては……」
(魔物……魔物ねぇ……)
茂みの中でぶつぶつとつぶやくクレイルの言葉が耳に入り、ラヴェルは思わず手の中にあったものを握り締めた。
付け根の部分しか残っていない、クリスタルのペンダント。砕けて尖った箇所が、手のひらに突き刺さる。
「司祭様のお力で何とかなりませんか」
沈黙に耐えかねたように、母親はなえた体をベッドから起こした。
「魔物ならば、聖職者の司祭様のお力で……」
懇願する沈痛な声に、司祭は難しい顔をして首を左右に振った。
「我々ごときの力ではどうすることもできぬ。それこそ、セラか魔物ほどの力でもなければ……」
悲嘆に暮れる夫妻をなだめ、その司祭達は重い足取りで帰っていった。
茂みの中で息を潜めている二人の耳に、やがて再び家の中の声が流れ届いた。
「ああ、どうすればいい? 子供が魔物に食われてしまう」
「司祭様のお力でも魔物を退けるのは無理だなんて……一体誰に頼ればいいのです?」
やせ細った手を女性は赤子の頭にのせた。
「この体では二人目は無理だし、この子は何としても……」
「ああ……そうだ、魔導士様に相談しよう。こういうことにはお詳しいはず」
夫婦が相談する声に我に帰り、再び家の中を覗いてみれば、夫妻に抱えられた赤子は何も知らないようによく眠っている。
やがて夫婦は寄り添うようにしてどこかへ出て行った。
その後ろをラヴェルとクレイルもついていく。
先程から何かが引っかかっているのだ。
その夫妻は村外れの館に入って行った。二人もまた窓から覗き込む。
「……というわけなのです」
夫婦の説明に五人の魔導士達は何やら相談を始めた。やがて重い口調で二人に告げる。
「その子の運命は残念だが変えられぬ。人間ごときには運命を変えるなどということは出来ぬのだ。三人の女神に抗しうる力など、人間は持っておらぬ。回り始めた時の歯車を止めることは、我々にも出来ぬ」
残酷な答えに母親は声も立てずに涙を流し始めた。
さすがに心が痛むか、魔導士達は分厚い本を開いて色々と相談を始めた。
やがて気が進まなそうに、ある一人が一つの案を出した。
「禁じ手ではあるが……命の秘儀を使うという手もある」
「命の秘儀か……」
別の魔導士が一斉に眉をひそめる。相当な禁じ手であるらしい。
だが夫婦は構わなかった。
「お願いです、それが何だかは分かりませんが、子供を得られるなら何をしても構いません。お願いします」
「しかし……」
「お願いです!」
顔を青くして泣きつく母親に、魔導士達は重い腰を上げた。
「……仕方あるまい、非常事態だ」
魔導士は隣の部屋に夫婦を招き入れた。棚には薬品壺などがぎっしりと並んでいる。
「禁じ手だが仕方あるまい。その子を失う事は我々には止める事はできぬ。ならば……」
最長老が振り向いた。
「その子を魔術でもって二人にわける。魔物が来たらその増えた子供を身代わりに差し出すと良い。ご夫妻は自分の生んだ子をそのまま育てると良かろう。たとえ元の子供が連れ去られても、分身は残る」
魔術で人の命を操作する。
考えによってはおぞましい案に窓の外の二人は顔から血の気が引くのを感じたが、室内の夫妻はとても喜んでいるようだった。
「その赤子に傷を付けることになるが仕方あるまい。覚悟は良いな?」
「はい、お願いします」
頭を下げる親の腕の中で、何も知らぬ赤子は無邪気に室内を見回している。
その子を腕に抱え、やがて魔術師達は奥へと姿を消していった。
|
時折意識が遠くなる。
あやふやな景色と音。
幻影の流れる中にいるのだから仕方ないのかもしれない。
気がつけば、二人は魔術師の館ではなく、小さな村に立っていた。
慌てて夫妻と赤子の家を探し、窓の外からそっと中を覗いてみる。
時間の感覚がずれているのは分かっていたが、どうもかなりの時間が経ったらしい。
赤子だった子供がよちよち歩きをしている。
そして。
生まれたばかりのような赤子が揺りかごの中に眠っていた。
子守唄のまねでもしているのだろう、少し大きくなった子供が言葉にすらなっていない言葉を歌うように口に乗せている。
そのあどけない声にラヴェルもクレイルも気を取られていたが、まぎれて聞こえた母親の言葉に背筋が凍りついた。
「ごめんねレヴィン、痛かったでしょう。でもこうでもしないと私達には子供が……」
!!!!
(あああっ! やっぱりここ、彼の記憶の中だ)
(じゃあ、あの子供がレヴィン!?)
何をされたのか、レヴィンらしき幼子は左手の指先に包帯を巻いている。
その様子は痛々しいが本人は何もわかっていないようで、ふんふんとご機嫌で何か歌っては笑っている。
だが、突然何かの意識がその風景を浸食した。
頭を抱えていたクレイルと顔を引き攣らせていたラヴェルの二人は、何かの気配にそろって茂みに飛び込んだ。
息を殺してしばらくうかがっていると、得体のしれない黒いローブをまとった、いかにも、といった感じの神官が現れた。
禍々しさを隠しもしないその姿は、神か魔物か知らないが、忌まわしき者を崇める暗黒神官であろう。
そのうちの一人がすっと手をかざすと、家のドアが黒い霧になって溶けた。
神官四人が音も上げずに家の中に姿を移す。
中から声にならない悲鳴が聞こえた。
掴んでいた木の枝を投げ捨て、ラヴェルとクレイルは家の中へ踏み込んだ。
部屋の中では暗黒司祭が子供を奪い取ろうとしているところだった。
「ゾンネン・ブラントっ!」
クレイルが素早く魔法を紡いだ。生み出された太陽の炎は一人の暗黒司祭にまとわりついたが、なぜか光術ともあろう魔法が何の効果も示さない。
「あ、あれれ??」
自分の手を見つめるクレイルの横でラヴェルも抜いたレイピアを振るっていたが、刃は確かに神官を貫いているのに手ごたえが全くない。
「王子……これも……幻?」
困惑しながら部屋の中を見渡すと、室内は荒れに荒れていた。
慌てふためく夫妻はそれでも取り乱すことはなく、用意しておいた揺りかごの赤子をさっと神官に差し出した。
しかし神官はそれには目もくれなかった。
魔法で夫妻を吹き飛ばすと、部屋の隅で誰にも守ってもらえずに怯えていた子供を、レヴィンらしき子供を掴み、そのまま忽然と消えた。
「ああっ!」
思わずラヴェルは声を上げた。
子供が連れ去られたからではない。
何かが見えたのだ。
言葉に出来ない恐怖が襲ってくる。
目だ。小さな子供の目。
見開かれた瞳が、絶望するような色を宿して、その親を見ていた。
|
「ラヴェル、ラヴェル」
耳元で誰かが呼んでいる。
いつの間にか倒れこんでいたらしい。
クレイルに抱えられてようやくラヴェルは身を起こした。
「大丈夫かい?」
「え、ええ……」
体が震えている。
とても怖い。
それが何故だかはわからないが、とにかく恐怖に身を包まれていた。
「少し落ち着こう」
「はい……」
しばらくそのまま過ごし、ようやくラヴェルは立ち上がった。
周囲を見れば、そこにあった家はいつの間にか廃墟のように崩れかけ、床も湿っている。カビや苔がびっしりと生え、むっとするような臭いが充満している。
先程まで人が住んでいたような面影は、ない。
「なあラヴェル、あれ、何だろう」
クレイルが何か見つけたようだ。
腐った揺籠に近付いて行く。
良く見れば何かが光っているようだった。
「これは……」
ラヴェルはその輝きを手に拾った。
クリスタルの小さな欠片だ。
森で拾ったレヴィンのペンダントと並べてみると、それは反応するかのように青い光を放った。
「きっとこれ、元々は一つだったんでしょうね……」
ラヴェルはそっとそれをポケットにしまいこんだ。
「ラヴェル、家の人も消えちゃったし、ここにいても仕方ないから外に出よう」
「はい」
村は先程までと何の変わりもなかった。子供が走り回り、老人は木陰で休んでいる。家畜の鳴き声が聞こえ、牧草の匂いがする。
「ラヴェル、取りあえず帰る方法を考えないと」
「そうですね……でもどうやって……」
幸い、村には他にも人が住んでいた。
もちろん彼らも幻かもしれないが、思い切って話しかけてみれば、返ってきた声にひとまず安堵する。
「おや珍しい、下の世界の人かね」
下の世界、ということはやはりここは上の世界……天空のいずこかなのであろう。
木陰の石に腰を下ろしていた老人は興味深げに二人を見た。
「ふむふむ、若いもんが随分と冒険をしたもんじゃのう。どうやって登ってきたね?」
「ええと……」
自分でも今の自分の状況を把握しきれていない。
それでも二人はああだこうだと今までの出来事をその老人に語って聞かせた。
「……と、いうわけなんです」
「ふうむ……他人の精神世界にのう? まぁ、わしゃ、ずっとここに住んでおるから、わしにとってここは普通の現実世界なんじゃがのう。ふうむ……」
老人はおもむろに考え込んだが、やがて杖で森を指し示した。
「村を出て東に進むと森に入る。一本道でな、だいぶ進むと突然目の前に巨大な扉が現れる。扉だけという不思議な物だが。遥か昔からあってな、昔話では全ての真実に繋がっていると言い伝えられておる。もしここが君達にとって幻の世界であるなら、君達にとって真の世界があるのじゃろう? だったらその扉をくぐってみると良いかもしれんよ」
丁重に礼を述べると、二人は自分達が倒れていた森へ再び分け入ってみた。
小道を進み、しばらくするとなるほど、木立の中に突然巨大な扉が現れた。
確かに老人の話の通り、扉だけだ。後ろに回っても扉の裏が見えるだけである。
「露骨に怪しいなぁ、これ」
「でもくぐってみるしかなさそうですね……」
「そうだねぇ」
重い扉を二人掛かりで押し開ける。
開いた空間には何も見えないが、進んでみないことには始まるまい。
二人は思い切ってその空間へ飛び込んだ。
妙な落下感にあっと思うまもなくラヴェルは床に叩きつけられた。
痛みに耐えながら何とか立ち上がるが、そこへ何かが降って来た。
|
ぐぎっ。
「いぎぎぎいいいいいいっ!?」
「わ、悪い!」
関節がずれるような音と、ラヴェルの声にすらならない悲鳴が響き渡った。
降って来たのはクレイルだった。
クレイルに押しつぶされ、重いものを持ち上げ損ねた老人のような奇妙な姿勢でラヴェルは固まっている。
「ラヴェル大丈夫?」
クレイルがうにゅと腕を伸ばした。ラヴェルの手をとって引っ張ろうとする。
「さ、さ、さ、触らないでぇっ!」
指で突っつかれるだけでも痛い。
「むーん、これはぎっくり腰だね……エア・ホーレン!」
「うぎゃあ!」
何も叩かずともよいのに、ばんとラヴェルの腰に手を当てると、クレイルは回復魔法を唱えた。
「よし、行こうか」
「は、はう」
ぎくしゃくとラヴェルはクレイルの後からついて歩き始めた。レイピアを杖代わりにして、呆れたようにしらじらと飛び交う燐光の中を進んで行く。
どうやらそこは暗い建物の中のようであった。
青黒い石材、波紋、なにやら色々な模様。
「ラヴェル、ここはアルスターの北の岬の、ほら、海底の神殿に良く似てる」
「帰ってこられたんでしょうか?」
二人とも淡い期待を抱いたが、進むにつれその期待は薄れていった。
確かに良く似ていたが、建物の構造が違う。同じ類のものを祭る神殿のようだが、海底の神殿とは別の神殿のようだった。
そうであれば魔物を祭る神殿ということだ。何が出てきてもおかしくないだろう。
二人は周囲の気配に注意を払いながら慎重に奥へと踏み入って行く。
警戒しながら進むとやがて広い空間へ出た。
薄い明かりが漏れている。人の気配に慌てて隠れ、柱の影からそっと中を覗いてみる。
「な、何ですかこれ!」
思わずラヴェルは叫んでいた。
ホールの中にはたくさんの子供がいた。
だがその姿は全て同じ。
「ラヴェル、ここってまだ精神世界の中だね、多分」
「王子、じゃあこれって……」
ホールにいる幼子は歳相応に可愛らしいが、その面影は村で見た子供と重なる。
「うひゃあ、彼も子供の頃は可愛かったんだ?」
見事に過去形の感想を漏らしながら、クレイルは手をその子供……恐らく子供の頃のレヴィンに伸ばした。
しかし、その指が触れることなく子供は霧のようにかき消えた。
「あ、あれれ??」
試しに別の子供にふれるとやはり消えた。
「王子、これも幻?」
良く見ればどの子供も影が薄く儚そうだった。
「ラヴェル、あの子だけ違わないかな?」
「え? あ、そうですね」
奥の壁際に膝を抱えて座り込んでいた子供だけ、しっかりと影がある。
ラヴェルが恐る恐る触れてみると、その子供は消えなかった。
だが、目の前に誰かが立っているのも触れられたのもわかっていないようだ。
寂しそうな悲しそうな、それでいてちょっと拗ねたような目をしている。
「あれ? 目が……?」
その目はラヴェルの見覚えのある赤い瞳ではなかった。
両目とも薄い藤色の、普通の人間の目だ。
その子供がシュンとしたように目を閉じると、その胸元で何かが光った。
「あっ、これは」
ラヴェルはそれに触れてみた。光ったのはクリスタルのかけらのペンダントだった。
試しにポケットから他の欠片を取り出してみると、反応するように全てが淡い光を放った。
その光に、やっと子供は目の前に誰かがいることに気付いたようだった。二つの丸い目でラヴェルをじっと見上げる。
可愛い。
ラヴェルの姿が見えているわけではないようだったが、それでもじっとラヴェルの顔を見つめている。
小さな手を伸ばし、その子供はラヴェルに触れようとしたが、その手がラヴェルに届く直前、その子供はクリスタルを残して消えた。
「これで三つ目……」
手の中に残された三つの欠片をラヴェルが見つめていると、横からクレイルも覗き込んできた。
「これはクリスタル? 何か一つの物が砕けたって感じだなぁ。レヴィンに関係するのだろうけど、何だろうね?」
ふと、クヤンと戦って敗れ、倒れていくレヴィンの姿が浮かんだ。
と同時に、初めて出会った時のこと、言われ続けた嫌味の数々に冷笑、語られた多くの知識や伝説、そして……目を閉じ、静かに横たわる姿。
「王子、この欠片を集めてみようと思うんですけど」
「そうだねぇ、何かわかるかもしれないからそうしようか」
つづく
|