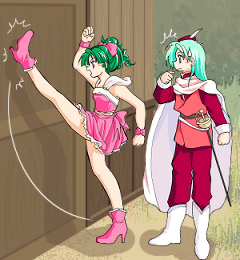|
がんばれ吟遊詩人! 〜ラヴェル君の場合〜
第一話:旅立ち(後編)

「あっはっは! ふーん、それは災難だったな」
しょげてるラヴェルの前でクレイル王子が爆笑している。
この王子様、名を正しくはクレイル・ディアマンテ・フォン・ウェーバーといい、このシレジアの王位継承権を持つ。
このシレジアの王族は光の力を受け継いでいる高貴な家系で、当然この王子もその力を扱える。
いうならば光のプリンスという所なのだが……いかんせん全く自覚が欠けている。
その力も使えて便利だなぁくらいにしか思っていないらしい。
そもそもラヴェルに竪琴を教えたのはこのクレイルなのである。
暇に任せて友人のラヴェルに教えてみたのだが……結果はこの通り。
クレイルは楽士、竪琴だろうがフルートだろうがリュートだろうが何でもござれなのだが、どうも弟子はいまいちパッとしない。
「はは……うん、今夜はここへ泊まっていくといいよ。あはは……ラヴェルらしいや」
「……ありがとうございます」
これで寝場所が確保出来たとほっとしたのも束の間……ラヴェルは思い出した。
この王子様、ラヴェルが来ると一晩中楽器の練習に付き合わせるのだ。朝までゆっくり寝られる可能性は限りなく低い。
案の定……。
次朝ラヴェルは目の下にクマを作ったまま広間へ姿を現わした。階段室を兼ねるその広間の床はいかにも森の豊かな国らしく、微妙に色の違う樫材が様々な模様を描き、その上に真紅の絨毯。部屋の正面には王家の紋章の入った国旗が誇らしげに掛かっている。
「やぁ! おはよう」
ニコニコ脳天気なクレイルとは反対にラヴェルの挨拶はどんよりしている。
「……おはようございます」
昨晩はほとんど寝られなかった……というより寝させてもらえなかった。
それでもこうして朝の挨拶に出て来たのだ。
そのままクレイルとともに朝食を摂りに行く。当然他の王族と一緒。少々堅くなりながらマナー通りに食を進める。部屋にいるのは国王と王妃、クレイル、その妹姫のマリア、そしてラヴェルと給仕。
ラヴェルがデザートに柘榴と蜂蜜のシャーベットに巴旦杏のスライスをかけたものをつついていると、横にクレイルが椅子ごと移動してきて話しかけてきた。
「それよりラヴェル、今度の旅は急ぐものではないんだろ? ちょっと頼まれて欲しいのだけど」
「はい、何でしょう?」
「実は大切にしていた宝石箱が盗まれてしまってね、取り返してきて欲しいんだ」
「何かあまり穏やかな話じゃありませんね」
「まぁ、君だったら剣の腕も少しは立つし……犯人は多分、最近暴れている山麓の盗賊団だろう」
貴族の館などがここ数か月立て続けに狙われて荒らされているのはラヴェルも噂に聞いている。今のところ幸いラヴェルの家は無事だが。
「でも何でこの警備のしっかりしている王城が?」
ちなみにラヴェルの父・ベルナール男爵も剣技の指導のかたわら警備に当たっている。その息子ラウディも見習騎士として警備に当たっている。
「いやー、最近城下の町でもスリとか多くてね、衛兵では手の足りないところもあるらし
くて城の警備兵達をまわしたんだ。そうしたらこの有様さ」
ラヴェルも財布をすられたばかりだ。
シレジアという国は全体的にどこかのんびりしているので、スリたちにとっては格好の仕事場なのかもしれない。
「はあ……そう言うことでしたらお引き受け致しますけど……」
「ほんと? 助かるよー」
「でもあんまり期待しないでくださいね」
クレイルが手をはたはたと振る。
「大丈夫! 駄目でもともとで頼んでるから」
がくっ……。
「中身はたいしたことないのだけど、箱がいいものなんだ。頼むよ」
恐らく盗賊なんて興味があるのは中身だから箱はそこらに捨てられている可能性もある。
「でも場所とかは?」
「それなんだけど、実は昨日の夕方スリを捕まえてね、ここの地下牢に入れてあるんだけど、彼に聞いてみるといい。スリって結構情報通らしいからね」
「蛇の道は蛇ですか」
「そ。まあスリといってもたいしたヤツじゃないから出してやってもいいよ。道案内くらいにはなるかもしれない」
「わかりました……あっ!」
話し込んでいる間にシャーベットはすっかり水になっていた。
|
階段室脇の通路から暗い階段を降りる。奥の鉄格子の向こうには人の気配。見張っていた兵士が今までのヒマに耐え兼ねたのか小声で話しかけてきた。
「実はこの扉の鍵、壊れてるのです。出ようと思えばいつでも出られるのですが、この男、
出ようとしないのですよ。タダで食事にありつける上に雨露しのげるからって」
シレジアという国は牢に放り込むだけでひどい拷問などは何もしないので、食いっぱぐれた者などが時折わざと捕まることもある。
今入っている者は単にドジを踏んだだけのようだが。
ラヴェルは試しにそっと鉄柵扉越しにのぞき込んでみた。
入っていた者と目が合う。
「ああっ!?」
思わずお互い同士が声を上げた。
「昨日のスリ!」
「昨日の女!」
そこにいたのは昨日のスリだった。
「……僕、男なんですけど。まあいいや、ちょっと聞きたいんだけど……最近貴族の館を中心に荒らしている、山麓沿いに拠点をかまえる盗賊達のことを知らないかな?」
「だったら情報量として銅貨五枚よこしな!」
「……あのね、君にすられてそんなお金持ってないよ」
「それもそうだ。勘弁してやるか」
「ああ、ついでにアジトを知っているなら道案内もね」
「おっ、つまり道案内している間は養ってくれるんだな? 食費と宿泊費を完全に払ってくれるなら引き受けてやるぜ」
現在の所持金は銅貨で三枚。自分一人の宿代もままならない状況なのだが仕方ない。
ラヴェルは無言のまま、自分の財布を逆さにして振って見せた。
ちゃり〜〜ん……。
牢にむなしい音が響き渡る。
わざわざ数えずともわかってしまうほど少ない所持金。
「仕方ねーなー。わかったよ、引き受けてやるよ」
言うと自分で牢から出てくる。やっぱりこの扉の鍵は壊れていたようだ。
「オレ様はアルトだ、よろしくな。お前さんは?」
「ラヴェルだよ。ラヴェル・ベルナール。取りあえず、よろしく」
詩人とスリというおかしな二人組みはそのまますぐに牢から出た。暗い階段に足音が響く。
その階段を上りきり、通路からホールに足を踏み入れた時。
目の前にドーンと立ちはだかる人影。
両手を腰にあて、見事に頬を膨らませた小柄な女性が立っていた。
「あーるーとー〜〜っっ! 何やってんのよ! わざわざ身柄引取りに来てやったわよ!」
昨日の宿屋で会った踊り子さんだ。どうもアルトと知り合いらしい。
「ごめんよー、ドジ踏んじまっ……」
「バカっ!」
どうもグルだったようだ。
しかしどうやって城へ入り込んだやら。
頭をかいているアルトの肩をラヴェルは後ろから指でつついた。
「アルト、この子は?」
「んー、こいつは……」
一応紹介しようとしたアルトを押し退け、その踊り子は愛想よく話しかけてきた。
「こんにちは! また会ったわね。私はルキータ。見ての通り踊り子よ。それより……」
そこで言葉を切ると、ルキータという少女は興味津々といった顔でアルトに向き直った。
そのままラヴェルを指差す。
「誰なの、この人。もしかして……」
続けて発せられた言葉に、ラヴェルとアルトは音を立てて同時にひっくり返った。
「カノジョ??」
ずがしゃぁっ!!
「こいつは男だっっ!」
無言で涙を流しているラヴェルやほとんど叫んでいるアルトの様子は無視し、ルキータは聞き返した。
「えっっ! アルトってそーゆーシュミだったの!?」
「ちがうっちゅーに!!」
「え? 違うの?なぁんだ、つまんない」
ちょっとがっかりしたらしい踊り子さんにラヴェルはアルトにしたよりも丁寧に挨拶をし
た。やはりかわいい女の子にはそれ相応の扱いをしなければ。
気を取り直して。
「えと、僕はラヴェル。駆け出しの吟遊詩人だよ。このシレジアの東、シュレジエンから
来たんだ。よろしく」
ウンウンとうなずくとルキータは二人の顔を交互に見るとまた聞いてくる。
「それよりお二人さん、どこへ行こうとしてたの?」
言葉だけは威勢よくアルトが答えた。
「盗賊どもを張り倒しに行くんだぜ!」
……足が震えて見えるのは気のせいだろうか。
「……張り倒されに行くんでしょ」
「違うって。オレ達が盗賊を倒しに行くんだ!」
「自分だって盗賊でしょ」
………………。
「……足、震えてるわよ」
「やかましい! これはむ、む、武者震いだっ!」
あごがカクカクしているところを見ると、どうあがいても武者震いには見えない。
「まぁいいわ。そう言うことなら私も付いてったげる」
「えっ!」
「さあ、そうと決まったら行きましょう! ぶちのめすのよ!」
いいと返事をしていないうちにどうやら決定になったらしい。
後ろで溜め息をつくアルト、財布を確かめるラヴェル。
そんな二人にはかまわずルキータはずいずい歩きはじめた。
「そうと決まったら支度を整えなくちゃね。まずは町で買い物よ」
いやな予感がする。
いくら数えても財布の中身が増えることはない。
自分の物くらい自分で買ってくれることを祈ろう。
|
爽やかな青空の下で買い物をすませると、三人は昼食を摂りに、そこそこ盛っている宿屋一階の食堂に入った。
しかし、いつもなら賑わっている食堂が、なぜか今日は人影はまばら、辺りも食事をする場にふさわしくないほど雑然と散らかっていた。
「なんだか散らかってるなぁ……」
見回すとマスターが床をモップで拭いている。その脇にごろつきが二人、青あざを作って転がっていた。
ぬれたモップが動くとともに皿のかけらがカチャカチャ音を立てている。
「おい親父、こんな真っ昼間から何があったんだよ?」
アルトが尋ねている間にも足元のごろつきから辛そうな呻き声。
「見ての通りさ。昼酒飲んで酔っ払ったこいつが暴れだしてよ、テーブルごとに八つ当たりしてほとんど部屋を一周したところでな、最後へきてあそこのテーブルの客にあっさりのめされちまったのさ。いや、ほんの一瞬の出来事さ、見事なもんだったよ」
アルトやルキータが部屋を見回している間、ラヴェルはしゃがむと呻いているごろつきの顔を覗き込んでみた。
「うっわー……ひどい顔」
……いや、別に顔のつくりが悪いと言っているのではない。腫れ上がっているのだ。
顔だけではない。腕もだ。頭にも見事なたんこぶが丘のように膨れ上がっている。
伸びているごろつきの大体のケガの様子を把握すると、ラヴェルはごろつきの腕の青紫に晴れ上がった所を指先でちょっとつついてみた。
「痛ッてぇ! そこはキズが……!」
大げさに床を転げまわって痛がるごろつきの様子に、ルキータは横合いからラヴェルを白い目で睨んだ。
「ラヴェル、あなたもなかなかひどいことするわね」
「え? そんなつもりは……」
ちょっと困った顔をするとラヴェルは何かつぶやいた。
そのまま手をごろつきの傷に当てると、かなりゆっくりだが、ごろつきの腫れが引いていく。
「ヘー、ラヴェルあなた魔法使えるんだ?」
「うん、ちょっとだけどね」
魔法が使えるといっても魔法使いと名乗れるほどではない。
シレジアの国は魔法研究が盛んで、魔術師は多い。
国の中では変態王子として知られるクレイル王子ですら、魔法の腕前だけでいえば、現代の五大賢者の一人として大陸中にその名が知れている。
そういう国の背景もあるかもしれないが、シレジアには魔法を教える学院も多く、裕福な家の子供は期間の長短を問わず、一度くらいは学院で学ぶものが多い。
また、魔法の中で基本とされる五つの魔法は、一般人でも使えるように簡単にアレンジされて、旅人達の多くに使用されていた。
「さーて、と」
かじった程度の超初心者以下の魔法でいい加減な手当てをすると、ラヴェルはごろつきに話しかけてみた。
「一体このケガはどうしたのかな? ん?」
「うう……。あ、あそこの野郎が……。気に入らねぇツラしてやがったから、ちょいとからんでやったらよ、うるさい、飯がまずくなる、とかなんとか言いやがって。かわいげがねぇから一発ぶん殴ってやろうと思って、襟首つかんでこぶし握ったらよ、次の瞬間には床なめてたんだよ、俺様が」
「返り討ちにされたわけだ?」
「ああもう、頭てっぺんに来たから立ち上がって本気でやってやろうと思ってよ、今度こそ拳一発繰り出してやったら、片手で軽く受け止めやがって! しかも、売られたけんかは買うことにしているとか何とか言いやがって! そのあとはわからねえ。気が付いたらこういう有様になって床にずっとはいつくばってるわけよ」
湯気すら吐きそうな勢いでごろつきはまくし立てたが、吐く息のアルコール臭さとは逆に、酔いはすっかり冷めてしまっているらしい。
「ふーん……まぁ自業自得だと思うけど。それで、君をこらしめた相手は?」
「あ、あいつだ。あの隅のテーブルの……」
震える指で示された方向を見ると……なるほど、暗い隅の席で男が食事を終えたところのようだった。
窓の外を眺めながら軽くエールのグラスを傾けている。
が、そいつは。
ラヴェルは嫌なことを思い出し、顔がすでに引き攣るのを通り越して歪んでいる。
「ああっ! あいつはっ!」
青い衣服、嫌な雰囲気。どこぞやの不良、いつかの吟遊詩人。
「……放っておけ、その程度の男に手当てなぞしてやる必要はない」
冷酷に言い放つ男の前で、ラヴェルはもう頭を抱えていた。
「ああ、また会っちゃったよ……」
「……嫌そうだな?」
嫌がるのが当たり前だと思うが、何も知らないルキータだけは何がそんなに嬉しいのか嬉々としている。
「ね、ラヴェル、あなた、あの人知り合い? あなたと違ってちょっとカッコいいじゃない。紹介してよ」
「そんなこと言われても……」
行く先々で会うので顔はわかるが、相手のことは何も知らない。もっとも、向こうはラヴェルのことを知っているようだ。
きっと亀のせいだ。
何かぶつぶつぼやいているラヴェルに、青ずくめの相手はおもむろに向き直った。

……考えてみれば相手をよく見るのはこれが初めてである。相手も腕と足を組みながらラヴェルをしげしげと見ている。
相手の男の髪はラヴェルと同じ、淡いミントグリーン。それは意外にも細く繊細な髪だ。
前髪の半分はわざと伸ばしているらしく、顔の右半面を隠している。左の前髪は上げられ、後ろ髪は短い。伸びた右前髪の下から湿布か絆創膏のようなものが少しのぞいている。左半面の顔は普通で頬にはやはり絆創膏。おまけに額にまかれているのはバンダナではなくて包帯。きっとけんかばかりしていて傷だらけなのだろう。
服装は白いシャツ以外すべて青。赤ばかり着ているラヴェルとは対照的だ。
上着の裾の赤い縁取り以外、マントからブーツからすべて青。そのマントは正面より少し脇で留めてある。
はっきりいってそこらのチンピラ以外の何者にも見えないが、赤い瞳は不思議な輝きを放っていた。
じっと見ると吸い込まれそうで怖い。
思わずラヴェルはぶんぶんと首を振った。
そのイヤミな同業者はいいかげんラヴェルを観察していたが、ふと脇にいるアルト達を指差すと尋ねてきた。
「……ところでこんなところで何をしている? お供達なぞを引き連れて」
「こんなところで悪かったな……」
床を掃き終え、ごろつきをつまみ出したマスターがポツリと呟くが、マスターにもラヴェルにも構わずアルトが聞き返した。
「お供達たぁ何だ? せめてお友達と言え!」
「あら、アルトって私のお供じゃなかったの?」
「誰がお供だっ!」
横で突発的に始まった痴話げんかに戸惑いながらも、ラヴェルはざっと今までの経緯を説明した。
「ほう……盗賊のアジトに宝石箱を取り返しにな? ふむ」
やかましいアルトを張り倒すとルキータが口を挟んでくる。
「悪人をぶちのめすのよ!」
「……威勢のいいことだ」
独り言のように感想を述べると、青ずくめは三人を見回すと考えるように腕を組みなおした。
「しかしな……お前達に盗賊どもに勝てるだけの力があるようには見えないが……」
確かに一応剣の訓練を積んでいるラヴェルはともかくアルトやルキータが戦力になるとは思えない。
持っているところを見るとアルトは短剣くらいなら扱えるのだろうが、あくまでも彼の武器は指先と口先である。ルキータにいたっては完全に丸腰のようだ。
もっとも、宝石箱を取り返して多少懲らしめてやればいいのであって、盗賊達を全滅させようとは思っていない。
戦いは避けるにこしたことはない。恐らくそうはさせてもらえないだろうが……。
「よし、俺が手を貸してやろう」
「ええっ!?」
……本気で言っているのだろうか。
嬉しさよりも迷惑さが頭をよぎる。
外れそうなほど顎を落として突っ立っているラヴェルの脇で、ルキータだけが喜んで飛び回っている。
「わお! そうこなくっちゃ。あなた、なかなか強そうだし、一人くらい仲間にカッコいい人がいなくっちゃ張り合いがないもんね。よろしくね、お兄さん。私はルキータよ」
「俺はレヴィンだ」
どうやらそういう名らしい。
しかし、手を貸してくれるのはありがたいが、いまいち嫌な予感。
アルトもあまり気乗りしないようで、ルキータの手形が付いたままの顔をラヴェルの耳元に持ってくる。
(なぁラヴェル、人数が増えただけ、報酬の分け前が少なくなっちまうぜ?)
(それはそんなに問題じゃないんだけど……)
(大問題だっ!)
ラヴェルにとっては報酬よりも行く先々でイヤミを言われるほうが問題である。
案の定……。
「さて、三流詩人、これからどうするのだ、すぐ発つのか?」
かくん。
もう何を言われても驚かないつもりでいたが、やっぱり言われればショックである。
音がするほどに首を折ったラヴェルだが、気を取り直して顔を上げる。
「い……いや、取りあえずお昼にしないと……」
「そうか、では待っていてやるから、さっさと済ませてくれ」
「う、うん……」
三人がポテトとグラーシュを突いている間、レヴィンは足元に置いてあった竪琴を手に、軽く歌い始めた。誰かに聞かせるでもなく、ただぽつぽつ歌っている。
ラヴェルにはそれが何の歌かはわからなかったが、伝承などにでてくる短い言葉が混ざることから、とても古い時代から伝わる歌であることはわかる。
部屋にレヴィンの、恐らく無意識のうちに声を押さえているのだろう、低く静かな歌声が漂う。
まるでつぶやくように。
|
アルトのいい加減な案内に幾度も道に迷いながらも、ラヴェル達は盗賊のアジトへ辿り着いた。
場所はシュレジエン南南東、山の麓の雑木林の中である。
寒い山岳地特有のがっしりとした太い木材で組まれた家屋。
かじっただけの、やはり初等のいんちき魔法。
ラヴェルの三流魔道士以下の催眠魔法で見張りに眠ってもらい、一行は壁の隙間や節穴から内部を覗いて見た。
まったく、運がいいのか悪いのか、盗賊団のメンバー勢揃いといった感じである。
中では賊のお頭以外の何者にも見えない風貌の男が幾人かの手下に何やら説明をしている。恐らく今夜あたり、どこかに盗みに入るつもりなのだろう。
さて、どうするか。
一行は声を落とすとひそひそと作戦を練り始めた。
(中に入ってキューってとっちめちゃいましょ。それが一番速いわよ)
(でも相手はつわもの揃いで、しかも七、八人いるよ。こっちは……)
ラヴェルはアルト、ルキータ、レヴィンの順に顔を見ると眉をひそめた。
(戦力になるのは僕とレヴィンくらいだし……)
なぜか感心するようにレヴィンが腕を組んだままラヴェルをしげしげと見た。
(ほう……? お前、戦力になるのか)
感心しているように見えるが言葉のイントネーションから明らかにバカにされている。
(……なるってば)
(ほおぉ、それではぜひ腕前を拝見させていただきたいものだな)
(………………。)
全然信じていない。
(よし、まかせろラヴェル、このオレ様が何とかしてやる!)
肩をつかまれて振り向くと、何やらアルトが自信満々でガッツポーズを決めている。
(まかせろって…一体どうするつもりなの?)
(まぁ見てなって!)
アルトは何を思ったか、一人でアジトの正面に回っていった。
(大丈夫かな〜〜……)
物陰に身を潜めて待っていると、勢いよくあけられる扉の音。
それにアルトの声が続く。
「おうおうおう、お前ら、シレジアの王城へ盗みに入った奴等だな! おとなしくこっちに盗んだ宝石箱をよこしな!」
「ああ? 何だ貴様は。宝石箱だぁ? 知らんなぁ」
思わずラヴェルは陰から這い出て中を覗き込んだ。
アルトが拳を突き上げている。はっきり言って全然迫力がない。
「おらおらおら、痛い目に遭わないうちにさっさと宝石箱のありかをはいちまいな!」
ラヴェルの横で、小さく舌打ちの音が漏れる。
(チ……つまらんお決まりのセリフを吐く奴だ)
レヴィンが面白くなさげに呟いている。
覗き込むラヴェルやルキータとは違い、壁を背に寄り掛かり、腕や足を組み、視線は森の彼方。
どうやら音と気配だけで中の様子を感知しているらしい。
そのレヴィンがすっと目を閉じた時、中から豪快な笑い声が響いた。
「はっはっはっ、痛い目だ? 坊や、そういう事はもっと貫禄を付けてから言いな」
「ンだとぉ!? 知らん振りしたってダメだぞ! おとなしく渡しゃあ見逃してやったっていいんだぜ?」
再び覗き込んでみれば、お頭らしき男が隣の男に目配せをしていた。
隣にいた大男ががずいっとアルトの前に立ちはだかる。
「な、なんだよ?」
迫力にアルトが思わず一歩引いた途端。
ごがん!
ベコベコになった鍋を叩き付けたような音を立て、岩のようなげんこつがアルトの頭を直撃した。
ひっくり返ったアルトの目から星がちらちら飛んでいる。
(あらら)
(やっぱり……。ダメねラヴェル。中に入るわよ)
ひとつ溜め息をつくと、ラヴェルが返事をする間もなくルキータが行動を起こした。
慌ててラヴェルは後を追い、後ろからは黙ってついて来るレヴィン。
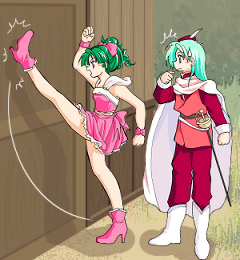
ルキータが細いヒールのブーツで扉を蹴り開けた。
なかなかの迫力である。
そのまま彼女はずかずかと入っていくと、お頭の前にずずいっと、ない胸を張って立ちはだかった。
「さぁ白状なさい、お宝はどこ!?」
盗賊達は呆気に取られている。
無理もないが。
「何だ何だ? お前らまさか俺たちの取り分を横取りしようってのか?」
やっと状況を飲み込んだらしい。
お頭は戸口からのそのそ入ってきた頼りなげな詩人とつまらなげなチンピラの姿を認めると、顎をしゃくった。
「おいお前ら、やっちまいな!」
屈強な手下達が刃こぼれした山刀などを手に取ると、負けじとルキータは叫んだ。
「さぁレヴィン、やっちゃいなさいっ!」
………………。
何でそうなるんだか。
深い溜め息を吐くと、それでもレヴィンはルキータの横へ並んだ。
そのまま斜めに構えてお頭を眺めるとニッとして一言つぶやいた。
「……フランメ……!」
その言葉が終わらないうちに室内に凄まじい爆発音が響いた。
むらっとする熱気に景色がゆらゆらと揺らめく。
その景色にラヴェルがハッとした時にはすでに勝負がついていた。
お頭以外……手下達のすべてが炎に焼かれて床に倒れ込んでいた。
(フランメ……黒魔法だ……)
魔法の中では基本とされる炎系魔法、その中級に位置するものだ。これが使えるなら胸を張って魔術師を名乗れる。
しかも今、レヴィンは呪文を唱えず、いきなり魔法の名だけで魔力を発動させた。
ただの乱暴な不良詩人かと思っていたが、恐るべき実力である。
「さて……残ったのは貴様だけだが……」
「ひっ!?」
残ったというよりわざと残したのだろう。じんわりと圧力をかける。
言葉だけなら大したことはないが、状況とレヴィンの持つ独特の雰囲気が重くのし掛かる。
今の一撃で気を良くしたらしく、横ではルキータが脅しにかかっている。
「ほらほらほら、さっさと白状しないと、真っ黒こげの炭オヤジになっちゃうわよ!」
いつもこんなことをやっているのだろうか。続けてレヴィンも物騒なことをいう。
「……よく脂が乗っているな。火を付けたらさぞかしよく燃えるだろう」
「ひいいっ!」
レヴィンもルキータも、それぞれに今の状況を楽しんでいるようだ。
ラヴェルはというと……のびているアルトの手当てで精一杯。ド素人のいんちきヒールでは、たんこぶと青あざの腫れを引かせるのがやっと。
そのラヴェルの後ろでは相変わらずルキータがきーきー叫んでいる。
がさっと音がした。
ラヴェルが振り向くとお頭が腰を抜かして床にへたりこんだところだった。
レヴィンが一歩前へ出て上から無言で威圧している。
(うーん、迫力……)
背中だけ見ていても怖い。
お頭どころかラヴェルまで気押されている。周りの異常な雰囲気に、やっとアルトも目を覚ました。
そんなことにはお構いなしに、室内にレヴィンの静かな声が響く。
「……なかなか口が堅いな。ならば……」
そこでいったん言葉を切ると、レヴィンはお頭の前にかがみ込む。
不思議な輝きをする赤い瞳で、真っ直ぐ相手の目を見る。
「……少々痛い目に遭ってもらうとするか」
「いいいいいっ!?」
レヴィンは無言ですっと立った。
お頭の声にならない悲鳴につられてよく見ると、その手をレヴィンがキリキリ踏んでいる。
「ふむ、まだ喋らないか……大した根性だ。それだけの根性があるのに盗賊なぞをやっているとは勿体ない」
ちらっとルキータに目をやるとレヴィンは足を外した。
「速くしゃべらんと……こいつに踏ませるぞ」
「踏んじゃうわよー!」
思わずラヴェルは視線をルキータの足元に落とした。
ルキータの靴のかかとは、こんなものを履いて踊れるのが不思議なほどに細いハイヒール。
「ひいいいいいっ! ご……ご勘弁を〜〜っ!」
「手に穴が開かんうちに話したほうが身のためだぞ」
「は……話します、話します!」
お頭の顔は、涙と鼻水でグショグショだ。
歪んだ顔を更にゆがめている。
「あ……あそこの、棚の二段目……置いてある……」
見ると、確かに上質な真紅のベルベット地に純金の縁取りを施した、少々古ぼけた宝石箱が無造作においてある。
ラヴェルが確かめると、中身はすでに空っぽだった。
しかし、箱の作りは見事なものだった。
「あ、なるほど。確かに箱が高価なんだ?」
「は……箱がだとぉ!?」
盗賊達は中身が目当てだったらしいが、持ち主のクレイルの話では、中身はクレイルがお忍びの際に町の露店で買ったいんちき物の指輪が二つか三つ入っていただけらしい。
ラヴェル達が箱に気を取られた一瞬に、お頭は脱兎のごとく逃げ出した。
「あ、逃げた!?」
「……放っておけ」
確かに、これだけのことをされれば当分大人しくしているだろう。
「そーだね……じゃあこれを持って引き上げようか」
ギギギ……ときしむ扉を開け、一行は城に向けて歩きだした。
しかし、二、三歩進むと、先頭を歩っていたレヴィンが何か思い出したようにふと立ち止まる。
「そう言えば……腕前をご披露いただく機会がなかったな」
「……なくていい、なくていい」
ラヴェルは必死で首を左右に振り続けた。
|
「きゃー、王子様だわ!」
はっきり言って全く見目は良くないのだが、ミーハー娘は王子様という生き物の姿を目の前にして一人で喜んでいる。
ただし、喜び方が若干微妙ではある。
陛下は外遊中でクレイルが城を守っていたのだが、玉座に座らず、こともあろうにその下の床の段差に腰掛けていた。
何でもこの玉座、建国以来という由緒ある代物のため、ミシミシと音がする上に安定が悪く、座り心地が悪くて疲れるのだそうだ。
「やあ、ご苦労さん。人数が増えているようだけど……報酬は変わらないからね」
クレイルはラヴェル一人を想定して報酬を用意していたのだが、道案内役のスリはまだいるし、見たこともない少女とチンピラのような男まで増えている。
後ろでアルトとルキータの不安げな声がもれた。
「ラヴェル、私たちにくれないなんて、言わないわよね?」
「大丈夫。公平にみんなで分けよう。じゃあ、人数で割って……」
報酬の金袋に手を突っ込んだラヴェルにルキータがストップをかけた。
「あ、それはやめ。働いたぶんに比例してわけましょ。その方が公平よね」
「そっか、それもそうだね」
アルトの目が俄然きらきら光りだした。
「お、じゃあオレ様は道案内を頑張ったってことで……」
「私にまかせて。こーゆー計算、得意なの」
ニンマリすると、ルキータはまだクレイルのいる前で包みを開いた。
中にはほんの一握りの銀貨と銅貨。
ルキータは思わず、ニコ目で突っ立っているクレイルをジト目で睨んだ。
「……意外とケチ臭いわね」
それでもパッパッと手際よくわける。
その速さにラヴェルが感心したのも束の間。
「ち……ちょっと待ってくれない?」
「だ・め・よ! 働いた分に比例、って言ったでしょ」
「で……でも……」
「待て待て待て、オレも納得いかんっ!」
「はいはい、時間切れ。次の機会に頑張ってね」
何とルキータ、銀貨と銅貨を十とすると、ルキータが四、レヴィンが三、ラヴェルが二でアルトが……たったの一、という配分でわけた。
「そりゃあないぜ、お前叫んでただけで何もしてないじゃないかよ!」
「あなたは気絶してただけでしょ」
「オレは道案内しただろうが。ラヴェルこそ何もしてねーじゃんか」
ぎくっ……。
手にしたわずかな報酬をラヴェルはコソコソと財布に押し込んだ。またアルトに取られるのは勘弁こうむりたい。
「ラヴェルはあなたの手当てしてくれてたのよ、感謝しなさい!」
ほっとしたラヴェルの耳にのんびりした声が入ってきた。
「納得いくようにわけたみたいだね。じゃあ僕はこの辺で……」
「納得行かんっ!」
目の前で始まった取り分を巡るしょうもない口げんかにクレイルはそそくさと出て行こうとするが、思い出したように入り口で振り返った。
「あ、じゃあラヴェル、旅、気をつけて行ってこいよ。じゃ!」
口の横辺りまで軽く手を上げると王子は小走りに逃げていく。その後ろを近衛兵が無表情のままついていった。
「さて、と。みんなはこれからどうするんだい?」
主のいなくなった玉座の間で、ラヴェルは他の三人を見回した。
「僕はやっとお金も出来たし、国外まで足を伸ばすつもりでいるんだけど」
最初から国外へ行くつもりだったラヴェルだが、なんやかんやと足止めを食ってしまった。
今度こそ国外へ足を向けたい。
「おもしろそーだな、よし、このオレ様がついていってやるぜ!」
「えっ」
「何か嫌そうだな?」
「あ、いや、そんなことは……」
アルトはついて来る気満々のようである。
あまり気乗りしないが、レヴィンについて来られるよりはよっぽどマシである。
「君は?」
「俺か……? 俺はまた適当にそこらをふらふら流れてみるさ」
レヴィンはどうやらついてくる気はなさそうである。どうやら一安心。
「じゃぁ私はねー、レヴィンについていくわっ!」
「ええっ!」
アルトとラヴェルの不満そうな声が重なる。
一度くらいかわいい女の子と二人で旅してみたかったのだが、アルトがついて来る上にルキータは別行動か。
「何か二手に分かれたけど……まあいいや、行こうか」
「じゃね、ラヴェル」
「また会えるといいね」
「さーぁ、どうかしら?」
つれない返事にラヴェルは無言で涙を流した。
ふう、やれやれとでも言いたげにレヴィンが溜め息を吐く。
「ではさらばだ、四流詩人。国の外でしっかり修行してこい」
………………。
……前より格が下がったような気がするのは気のせいだろうか?
「よし、行こうぜラヴェル」
「そうだね。じゃ、また!」
詩人と盗賊、チンピラと踊り子という二つのおかしな二人組みは、城館を出るとそれぞれ城門から旅立っていった。
バルコニーからいい加減に手を振るクレイルの姿が徐々に遠ざかっていく。
相変わらずシレジアの空は青く澄んでいた。
つづく
|