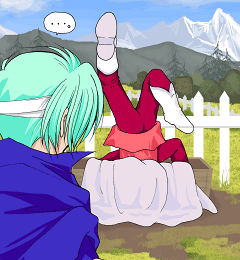|
がんばれ吟遊詩人! 〜ラヴェル君の場合〜
第四話:休息
柔らかな日差しを浴びて輝く木の葉。
その木立の中にレンガ造りの館が静かにたたずんでいる。
村の向こうのゆるやかな斜面には羊が草を食み、遥か遠くには東の帝国とこの国を隔てる高い山脈がうっすらとその影を浮かび上がらせていた。
揺れる梢が館の屋根に淡い影を落としている。
シレジア王国最東端、シュレジエン地方のとある村を預かる騎士の館、ベルナール男爵邸。
その一階の居間で、ラヴェルはソファに横になっていた。
東に面した窓から日の光が優しく差し込む。
寝るなら自分の部屋で休めばいいのだが、そういつまでもベッドに潜っているわけにもいかない。
傷はもういいのだが何となく体中がだるい。
怪しい洞窟で怪我をして寝込んでからそろそろ二週間が経つ。
ルキータはラヴェルというクッションがあったためかほとんど怪我もなく、押しつぶされたラヴェルだけがこうして寝込んでいたのである。
一人で戦った挙句にこんな怪我をし、しかも結局敵を倒したのはレヴィンなので全くもってカッコがつかないのだが。
「ゆっくりしていってね」
「はい、喜んで!」
ゆっくりも何も、ルキータ、加えてレヴィンまでこの館にすでに二週間も居候している。
幸いに母ベルナール男爵夫人もルキータが気に入ったと見えて、そろそろ出て行くようになどと促す気配はない。
男爵も息子のラウディもずっと城に出仕しているし、娘のシルヴィアもほとんど家にはいない。
いるのは夫人と、いつもより更におとなしいラヴェル、ルキータにレヴィンだけ。使用人も男爵と共に城へ出仕している。
母親がキッチンへ姿を消すとルキータはチェストに腰掛けた。
「ね、ね、ラヴェル。あなたのお母さん、凄く優しい人じゃない? キレイだし。お父さんて人もとってもダンディ。妹も美人さんだし、何より弟さん! すご〜いハンサム! きゃ! この幸せ者!」
どうもルキータは外見が良いのが好みらしい。ラヴェルから見てラウディは確かに悪くはないが大騒ぎするほどの美形でもない。
まぁ、女性とは見る目が違うかもしれないが。
「それにしても……そう、み〜んな美形タイプなのに、なんでラヴェルだけ違うのかな?」
………………。
「それは悪ぅござんしたね〜〜っ!!」
「ふ……」
半ばやけっぱちになっているラヴェルの視界に、窓辺に立っているレヴィンの後ろ姿が入る。
が、微かにその肩が震えている。
「……後ろ向いて笑ってるでしょ」
「……いや」
ラヴェルは横たえていた体をおっくうそうに起こすと、そのまま背もたれに寄り掛かった。
「うーん……。僕、本来はここの家の者じゃないんだよ。養子っていうか、預けられたんだよね。よく知らないけど、僕の産みの親らしい人の話はちょっと聞いたことがある。育てるのに困っていたみたい。なんか凄く貧しげだったって」
「分かる分かる! だってラヴェルって貧乏性だもの」
がくっ!
心底納得され、ラヴェルはがっくりと首を落とした。
「ま、まぁ、その人が僕を抱いてこの辺りをうろうろしてて、その時はまだここの夫妻にも子供がいなくて、それじゃあって、引き取ったんだって。で、僕をここの跡取りにするつもりだったらしいんだけど、二年経ったらラウディが生まれてねー。僕、跡取り養子から一転ただの居候」
「うっわー、超不幸、運なし! あなた、さては前世で日頃の行い、悪かったわね?」
前世なんて覚えていないが特別悪いことをしたことはないと思う……多分。
もしあのまま跡取りであったなら騎士にでもなって城に出仕、クレイルあたりに仕えているのかもしれないが、それはそれで良いような悪いような。
「それであなた、自分の親って人のところへ帰る気はないの? あ、もしかしてそれで旅してるとか?」
「ううん。旅してるのは好きでやってることだからね。帰るのは……どうかな、今ごろ帰っても多分僕だって分からないだろうし、その前に家がどこか知らないし」
「ふーん」
ラヴェルにとってはこの村が故郷であり、正直、生家がどこであるとかはあまり興味が向かないので、あまり考えたことがない。
ラヴェル自身がこの村やここの両親を気に入っているし、居心地も悪くない。
「でも何かその親らしい人、山を越えて来たって感じだったらしいから、ひょっとしたら中央高地辺りの出身かもしれないね」
「へえ〜。中央高地か。いいじゃないの」
中央高地とはシレジア南に位置する都市国家の林立する地域で、それらがまとまって連合国家の形態を取っている。
一応その中心の役割を担っているのはハイランドという都市で、盟主は連合都市国家の有力者から数年ごとに選ばれ、次期王にはすでにウィンザイル第一公子シルトが内定している。恐らくルキータはおろか、かなりの数の女性がファンになりそうな容姿の騎士だ。
「ところでルキータはどこから来たの?」
「私? 私は帝国よ。その帝都。バリバリのヴァレリアっ子よ! 私のいた一座は帝国でも指折りの一座で、私はそのスターなんだから!」
自慢げにまな板胸を張ってみせる。
なるほど、あか抜けているとは思っていたが帝国の出身とは驚きだ。ヴァレリア帝国といえばこのミドガルド世界で最も巨大で繁栄している、有史以来まれにみる一大帝国だ。
文化も栄え、宮廷文化の他にも、庶民たちに親しまれる大道芸なども発達、旅芸人の一座も数多くある。
もっとも証拠はないので、ルキータが本当にどこかの一座に所属しているかはわからないし、スターだというのもあくまで自称で怪しいが。
「……その大スターがここでこんなことしてていいの?」
「気にしない気にしない、ちょっと退屈してたから気晴らしに出てきただけよ。そのうちには帰るって。それより、レヴィンはどこから来たの? 私、何も聞いてないわよ」
そういえばラヴェルも、今はいないがアルトだって恐らく彼について何も知らないだろう。レヴィンは自分から何かを話そうとはしない。
イヤミ以外は。
「そういえば僕も何も知らないな」
「そうそう、謎の風来坊」
突然話題を振られ、やっと気付いたようにレヴィンは振り向いた。
「俺か? 俺はな……」
言いかけてふと考え込む。
「……いや、今はやめておこう」
「ずるーい! 何か話してよーー!」
ルキータが不服げに頬を膨らませた時、キッチンの向こうから母の声が掛かった。
「ルキータさーん、ちょっと手伝って下さらなーい?」
「あ、はーい、今行きまーす!」
彼女は駆け出したが居間とホールの境の辺りで振り返った。
「後で話してね」
|
ルキータが昼食の用意の手伝いに姿を消してから、喧しかった室内に静けさが戻った。
外の風に葉が揺れる音や小鳥の声、遠くから微かに羊の鳴き声も聞こえる。
恐らく外に出ていれば気にもしないほど弱い風ではあるが、部屋の中のテーブルクロスの裾や花瓶の花などがゆらゆらとそよいでいる。
その様子を窓ガラスに映し見たのか、レヴィンが窓を閉めた。
白い窓枠とその向こうに広がる風景、レヴィンの姿、その窓を閉める意外にも優雅な手つき……全ての雰囲気が何となく不揃いなのに、どういう訳か、見ていて不似合いには感じない。不揃いなのになぜか調和している。
いつの間にかうとうととしかけたラヴェルの耳に、どうでもよさそうに呟くレヴィンの声が微かに聞こえた。
「俺はな……」
やはり何気なくつぶやくように続いた次の言葉に、寝ぼけているラヴェルは適当に相槌を打った。
「アスガルドから来た……」
「ふーん、アスガルドね……」
………………。
「……え?」
とてつもなく違和感を覚えた言葉に、ラヴェルは今頃になって飛び起きた。
「……アスガルド!?」
目をこする。まだ寝ぼけているだろうか。
耳を疑ったラヴェルは聞き返した。
「アスガルドって……あのアスガルド?」
「……多分そのアスガルドだ」
ほとんど会話になっていないが、ラヴェルはその単語を何度も頭の中で反芻した。
レヴィンは窓の外を向いたままだ。風景を眺めているのではないだろう。一体その赤い瞳にはが映っているのか。

その後ろ姿に再び問い掛ける。
「……からかってないよね?」
「疑り深い奴だな、お前も」
今までの経過を考えれば当然だと思うが、しつこくラヴェルは繰り返した。
「アスガルド……本当にある土地なの? おとぎ話の世界じゃなかったのかい?」
「実際にある世界だ」
レヴィンはゆっくりと体ごと振り返った。
「この、ミドガルドの上空にな」
「!?」
このミドガルド世界の神話では、世界はまず一番の空の高みに神々の大多数が住むといわれる天上界ヴァルハラがあり、神界とも呼ばれている。その下にその下僕やドラゴンなどの住む天空界、その下に我々の住む中津国、地上界ミドガルドが横たわっている。
その他に、どこにあるか分からない、死者の国といわれる冥界ヘル、やはりどこにあるのか不明な物質的な存在ではないといわれる妖精界、そして……伝説の地、アスガルド。
世界は九つあり、それらを宇宙樹と呼ばれる大樹が貫いているという。
その九つが何世界かは伝説に詳しい詩人や学者によっても意見が割れるところである。
「なっ……上空って……じゃあ、アスガルドっていうのは……」
「お前たちが天空界と呼んでいる世界の真の名だ」
伝説ではアスガルドとは不思議な空間で、その空間に幾つも島が浮いているという。
古い言い伝えによると、古代ミドガルド世界の魔法的秩序が崩れている時期に、当時の世界を保っていたエネルギー的なバランスまで崩れ、しかもそんな時に限って、ある魔術師が自らの能力をわきまえずに行った魔術の実験でその魔力が暴走、古代ミドガルド世界の大部分を空高くまで吹き飛ばしてしまった。
それこそ禁呪のいわれであり、以降、その吹き飛んだ大陸は島々となって空に浮いているという。
そこには地上にはいない不思議な種族も多く住む。地上では滅多に出会わないドラゴンやペガサスが飛び交い、美しい妖精、例えばシルフなどが舞い、より美しく神秘的な天空人が住んでいるという。
「天空界……えっ? じゃあひょっとしてレヴィンって……天空人??」
「そういうことになるな」
………………。
「……えーと」
伝説によると天空人とはその名のとおり、天空界に住む民。魔法に長け、ミドガルドではすでにわれている古代からの魔法……様々な歴史から禁呪と呼ばれているが……さえもいとも簡単に扱うという。
神話をモチーフにした絵画や彫刻では緩やかな白く薄い衣をまとい、背には一対の純白の翼を持った、天使にも似た姿で表される神秘的な種族。
………………。
「そーには見えな……」
「何か言ったか?」
「う、ううん! 何にも!」
無意味ににこやかに、それでいて背中にはぐっしょりと冷や汗をかきながら、ラヴェルは必死に首を横に振った。
目の前にいる自称天空人ははどう見ても神秘的には見えない。ラヴェルの目にはどうしても街の一匹狼風の不良兄ちゃんにしか見えない。
だが言われてみれば言葉にはできない不思議な、いや、不気味にさえ感じられる雰囲気がレヴィンにはある。
(そっか、それで禁呪が使えるのか……)
先の洞窟の隠れ神殿でラヴェルのピンチを救ったのはレヴィンの魔法だった。
それは見たこともない魔法だったがラヴェルには直感でそれが伝説にしか名を残さない古代魔法、つまり禁呪だと分かった。
信じがたいことではあるが、これでラヴェルの頭の中には一本の糸がつながりを見せた。
天空人なら強大な魔法を簡単に扱ってもなんら不思議はない。やはりあの魔法は禁呪だったのだ。
「でもなんで地上に降りてきたの?」
レヴィンの横顔を見ながらラヴェルは勝手にいろいろと想像した。
そもそもレヴィンは全く天空人らしくない。伝説のような美しい種族だなんて微塵も感じられないのだ。
(まぁ、おおかた乱暴が過ぎて落とされたんだろうけど)
微妙な殺気にはっとして視線を上げると、レヴィンがその赤い目でこちらを見据えている。
「お前、殴っていいか?」
「あっ! 冗談、冗談ですってば!」
口には出さないでいたのだが、心の中で思ったことを読まれていたらしい。迂闊なことは考えない方がいいようだ。
一度はチェストに腰掛けたレヴィンだったが、またゆっくりと立ち上がると窓の外を眺める。その後ろ姿の向こうに窓に映る顔がうっすら見えるが、表情までは読み取れない。
ぽつりと呟かれた言葉は意外なものであった。
「弟を……探している」
「弟?」
このレヴィンの弟……。
(まさか、弟もこんな性格してるんじゃ?)
こんな迷惑な人物が二人。
血は争えないって言うしね……などと思わず思ってしまったラヴェルだが、突き刺さるような視線に慌てて首を横に振った。
「あ! 何でもないですっ!!」
「ふん」
振り向きかけた顔はまた窓の外に向く。
「そいつを探してそれこそ世界中を彷徨ったが……アスガルドにミドガルド、アルフヘイム……。どこを探しても見つからないでいる」
「うーん……」
この地上界ミドガルドはともかく、アスガルドは伝説の土地、アルフヘイムというのも確か古い言葉で妖精界のことだ。
現実感の乏しい言葉にラヴェルは今ひとつ話についていけない。
「いや、探そうにも顔すら覚えていないのだ。何せまだ俺は二歳になるかならないか、弟だって産まれてから何週間も経っていなかったはずだ」
どうやらレヴィンはのんびりのほほんと暮らしてきたラヴェルとは比べ物にならないほどの苦労をしていたようだ。
だとしたら、この斜に構えたような態度、冷めた雰囲気、すでに人生悟っちゃったような感じもわからなくはない。
「そっか、大変なんだね……あれ? レヴィンて、年、幾つ?」
「二十三だが」
「にっ……二十三!?」
確かに、外見はそんなものだが、性格がやたらと大人びているというか何というか。
「二十七か八くらいかと思ってたよ」
レヴィンは腕組みをしたままあきれたような顔で振り向いた。
「お前と比べるな。お前は幼すぎだ」
「う……」
認めたくはないが反論も出来ない。
言葉に詰まるラヴェルなどお構いなく、レヴィンは独り言のようにまた何か呟いた。
「俺はアスガルド下島の辺境の村に転生して……」
その言葉を上書きするようにルキータの甲高い声が向こうから響いてきた。
「お昼にしましょーー!」
レヴィンが視線だけキッチンの方へ向けた。
「チッ、邪魔が入ったな。……まぁいいさ、今の話は忘れてくれ」
そういうとダイニングへ歩み去っていく。
「レヴィン……」
ナイフとフォークの音だけがカチャカチャと鳴っている。
「ね、私が作ったのよ! 美味しいでしょ」
ダイニングは微妙に静かだった。
ラヴェルもレヴィンも無言。美味しいとも不味いともいわない。
ラヴェルはナイフを置くと口に水を含んで一息ついた。
ちらと視線を横に走らせると、ただ黙々と料理を口に運ぶレヴィンの姿。
「ちょっと、美味しいかって聞いてるのよ。何か一言くらい、言いなさいよ」
グラスを置いたラヴェルとちょうど料理を食べ終わったレヴィンが同時につぶやいた。
「……ケイン・アンメルクン(ノーコメント)」
今まで旅の道中も野宿の際はラヴェルが料理を作ってきた。
何だか使い走りにされているみたいに思っていたが、ラヴェルはこれからも料理は自分で作ろうと、あきらめ半分に決心した。
|
「ぐ〜〜てん、もるげんっ。おはようラヴェル」
あくる朝、ラヴェルはこの家の住人でない珍妙な生き物に毛布をはがされて叩き起こされた。
「……へぁっ!?」
寝ぼけ眼をこすってよく見れば、ラヴェルの室内に入り込んできたのは、こともあろうにこの国の王子たるクレイルであった。
はて? 出仕していた父が連れ帰ったのであろうか?
しかしまだ今回の出仕期間は終わっていないはずである。
「やぁ、やっとお目覚めかい?」
「あ、ああ王子、おはようございます」
クレイルはラヴェルのポットを使って勝手にお茶を沸かすと、のんびりと一人で飲み始めた。
「王子どうしてここへ?」
「んー、近くまで視察に来たからついでに寄ってみたんだよ」
この国はまだ王も健在、クレイルは騎士ではないので軍の運営もなく、正直あまり仕事はない。
視察とはいえ、実際はいつものお忍びの食べ歩きだろう。
「男爵に聞いたんだけどケガしたんだってねぇ? 大丈夫かい?」
「ええ、まぁ、なんとか」
「ふうん、どれどれ?」
クレイルはぷにぷにした手をラヴェルの額に押し当てた。
柔らかな光がラヴェルを包む。
「うん、これくらいならもう大丈夫だね」
性格はともかく魔法の腕は一流のクレイルである。
何か適当に呟くとラヴェルに回復魔法らしきものをかけてくれた。
「国の外まで足を伸ばすっていってたから帝国方面へ行ったのかなと思ってたら、ケルティアへ行って来たんだって?」
「あ、はい」
本当はラヴェルももう少し各地を回ってきたかったのだが、あいにくケガのために断念、一度こうして自宅へ戻ってきたのである。
「えーと、ディアスポラ経由でケルティアへ渡ったんですけど、ほら、フィアナ騎士団の方に会いまして。なんだか戦になりそうでクヤン様に調停してもらいたいって言うのでまたディアスポラへ戻ってクヤン様と同行して、それでケルティアをアルスターからコノートまで行ってきました」
「へええ、じゃぁケルティア縦断だね」
「そうですね」
言われてみてから気づいたが、ケルティアを最北部から最南端へ旅したことになる。
「クヤン様はお元気だった?」
「ええ」
クレイルはクヤンとは面識があり、たびたびディアスポラを訪れている。
シレジアの王子とケルティアの国王という政治上のこともあるが、それ以上にクヤンは聖騎士として、光の血筋にあるクレイルを大事にしている。
「ああ、そういえば魔物がどうとかおっしゃってましたけど……何て言ったかな、忘れちゃいました。王子は何かお感じになります?」
「いや、全〜然」
気楽げにクレイルは手を振って見せた。
「僕は何にも感じてないよ。魔物騒ぎの報告も上がってきてないしね。とっても平和」
平和なのはクレイルの頭なのではないかと疑いたくもなるが、とりあえず外は相変わらず天気も良いし、優しい風が吹いている。
「それよりラヴェル、天気も良いし、どう? 少し出かけてみない?」
「え? どちらまで?」
「そこらへん」
仕方ない、ラヴェルは起き上がるとマントを羽織った。
一階の居間ではレヴィンとルキータがくつろいでいるようだったが、特に声もかけず、クレイルと二人で村の外まで足を伸ばしてみることにした。
森の中を軽く散歩してみる。
「やぁ、心地良いねぇ」
「そうですね」
田舎の風情を満喫してご機嫌のクレイルの横で、ラヴェルは茂みに絡み付いていた蔓を引っ張った。
淡い桃色の小さな瓜の仲間がなっている。
それをカリカリかじりながら、二人は村の東の牧草地の上へ出た。
牧草地は丘の斜面に広がり、羊がのんびりと草を食んでいる。
斜面の下のほうには牛がおり、その辺りは大地が露出、木立をはさんで村へとつながっている。
「あれ?」
ラヴェルは視界に妙なものを見つけた。
羊が一匹踊っている。
いや、羊が踊るはずがないのだが、踊っているように見える。
「何だろあれ」
「んにゃ?」
ローブの袖に沢山の森の恵みを突っ込んでいたクレイルが、くわえていた瓜をぼとっと落とした。
「うわあ、珍しいものを見たよ。こんなところにバーゲストがいるなんてね」
バーゲストというのは主にケルティアに生息する妖精動物で、様々な獣に化けていたずらをする。
そのうち、その妖精獣につられたのか、あたりの羊が皆泣き喚いてあちらこちらを狂ったように走り始めた。
羊飼いが慌てふためいて羊を犬と追い回すが、一向に羊は一箇所に集まらず、酔ったように泣き喚いている。
「あーあーあー」
「ほら、いわんこっちゃない」
べーべーめーめー、鳴き声が丘を満たした。
斜面の下にいる牛が迷惑そうにこちらに尻を向ける。
「ラヴェル、バーゲストを捕まえちゃおう」
「は、はいっ」
ラヴェルはクレイルと共に、踊っているヘンな羊めがけて走り出した。
羊は二人に気付くとくるくると尻尾を回し、おどけたように駆け出した。
「こら、待てっ!」
ローブに木靴のクレイルが早く走れるはずもなく、ほとんど一人でラヴェルは羊のお化けを追いかけた。
「ああ、こら!!」
羊は背の高い草むらへ飛び込んだ。
ラヴェルはいそいでそれをかき分け、茂みを覗き込む。
「あ、あれ??」
確かにそこへ飛び込んだはずの羊がいない。
茂みの中には大きな石が転がっているだけだ。
「ヘンだな、確かにここへ飛び込んだんだけど……」
もうどこかへ飛び出しているかもしれない。
首をめぐらせてラヴェルがキョロキョロしているその下で、大きな石に足が生え尻尾が生え、ひょこひょこと茂みの外へ走り出す。
「ああっ!? 騙された!!」
やっと奇妙な石の正体に気付くとラヴェルは再びそれを追いかけた。
「待て待て待てっ!」
へんてこ羊はひょこひょこ飛び上がるように駆け回っている。
丘の斜面をラヴェルはそれを追って必死に走った。
羊は斜面の下に向けてかけていく。
「え? あ、あ、ああっ!?」
ごげしっ!
勢いがついたラヴェルは、羊が急に方向転換したのについていけず、そのまままっすぐ坂を駆け下り……柵に激突した。
むっくりと起き上がったときにはすでに羊は丘の上へ駆け戻って鳴いている。
坂を降り切っていなかったクレイルが羊を追うが、彼が走るたびにその袖や懐から瓜やキノコや木の実が周囲に零れ落ちている。
「ほうら、待て待て」
クレイルは羊に向けて手を伸ばした。
魔力が糸のように細く行く筋も伸びて羊のお化けを絡め取る。
「よぉ〜し、良い子だからおとなしく……」
動きを止めた羊にクレイルは急いで近づいた。
瞬間……。
「ふわにゃあっ!?」
ぐにゃぐにゃした泥に木靴を取られた。
ハデに転んだクレイルは脇にあった水桶を蹴飛ばし、しかも降り落ちてきたそれが頭を直撃した。
「むきゅう……」
星を飛ばしながらノックダウンしたクレイルをそのままにし、ラヴェルは再び羊を追いかけた。
しかし。
「え?」
その背後で洗い鼻息が聞こえる。
振り向けばそこには、斜面の下にいた牛が群れになって追いかけてきている。
「ええっ!?」
マントこそ白いものの、ラヴェルの服装はほぼ赤一色。
どうやら牛を興奮させてしまったらしい。
「いきゃあああっ! 助けてぇっ!」
凄まじい足音が地響きを伴って斜面にこだまする。
ごすっ!
「ぎゃああああああああ!!!」
牛の角に突かれ、ラヴェルは空中に放り出された。
落下して来た彼を別の牛が角で突く。
よく見れば牛の背中に、やはり黒と白の牛模様の……しかしよく見れば体型は山羊の妙な動物が乗っかっている。
ラヴェルの情けない悲鳴が村中に響き渡った。
|
「……何をやっているんだあいつは」
窓から流れ込んだ聞き覚えのある悲鳴に、レヴィンは弦の調律をしていた竪琴を置いて牧草地を眺めた。
「……ほう?」
遠くで妙な羊が踊っている。
「何あれ?」
「バーゲストだな」
ルキータも興味津々と言った様子で踊る羊と宙を舞うラヴェルを眺めている。
牛の背中から飛び降りた牛模様の山羊が、今度は牧草束に化けて斜面のうえからラヴェルめがけて転がり落ちている。
「ふむ……行ってみるか」
丘の斜面には羊やら牛やらが乱れ走り回っている。
羊を追っていたはずが牛に追われ、ラヴェルは牧草にまみれた挙句にぼろぼろになりつつも、斜面をクレイルと共に走り回っていた。
「あああ! 誰か助けて〜!」
時々、ありもしない石につまづいたり突然足元に生えてきて激突する木はバーゲストの悪戯だろう。
ぶひひひひーん!
「いきゃああああああ!?」
牛に小突き回され突き飛ばされたラヴェルはあろうことか馬の尻に激突、そのまま両後ろ足で高々と蹴り飛ばされた。
背中に蹄跡をつけた赤いものが、レヴィンのすぐ脇にあった飼い葉おけに頭から突っ込んだ。
「随分な暇つぶしだな」
それを足先で突きながらレヴィンは遠くにいる羊のお化けを眺めやった。
「ふむ?」
草むらの中に沈んだクレイルの上に羊が寝そべっている。
「まったく、何でこんな奴にてこずっているんだ」
レヴィンは呆れたようにため息をつくと、村の厩舎から使われていない蹄鉄を拾ってきた。
見た目に反してかなりの重量があるが、レヴィンはそれを軽々と羊めがけて放り投げた。
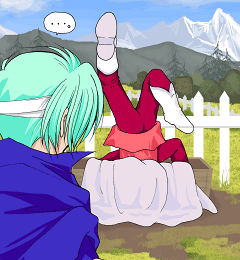
ごすっ!
鈍い音を立て、それはクレイルの頭を直撃した。
彼の上にいたはずのお化け羊は跡形もなく姿を消している。
「これで当分はここへは来ないだろうよ」
妖精は鉄を嫌うといい、とくに馬の蹄鉄を嫌う。
見渡せば狂ったように暴れていたほかの羊は落ち着きを取り戻し、興奮していた牛も元通り草を食んでいる。
「おい、生きてるか?」
バーゲストはいずこかへ逃げ去ったらしい。
落ち着きを取り戻した牧草地のはずれで、ラヴェルはまだ飼い葉おけに頭を突っ込んでいた。
スープの中にゆらゆらと小さな瓜が浮かんでいる。
多くの野菜や森の恵みのキノコと共に煮込まれたそれは、見た目だけはおいしいポトフに見えた。
「やー、運動の後の食事は良いねぇ」
頭に巨大なこぶをこしらえたクレイルが瓜をナイフで突いている。
「せっかくの山の幸だから今日は豪勢に食べようよ」
ベルナール男爵邸のキッチンにはよい香りが漂っていた。
料理が趣味のクレイルは比較的なんでもおいしく作る。
しかし。
特別に気持ちをこめて腕を振るうと、その料理は何故か殺人的にまずい料理へ変貌するのだ。
微妙な沈黙が室内を満たしている。
一体今まで何回騙されただろう?
ひたすらまずい料理を前に、今度こそクレイルの料理は口にするまいとラヴェルは固く決心したのであった。
つづく
|