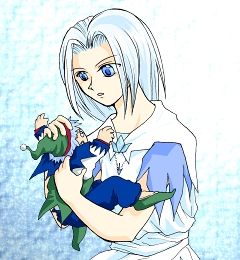|
がんばれ吟遊詩人! 〜ラヴェル君の場合〜
第九話:精霊(後編)
道はやがて一本の洞窟へたどり着いた。風穴であるらしく、あちこちに氷が張り付いている。
「これを抜けると集落で、そこの祠にジャック・フロストがいるんだね?」
「らしいな」
洞窟内は、目とカンのいいアルトを先頭に進むことにする。
彼も堂々巡りのせいでだいぶ疲れている模様。
「あ〜あ、何か魔法とかで一気に先へ進めたらいいのになあ。こう、歩かなくてもさ」
「そうね……」
ルキータがそう応じた途端。
「おわっ!?」
足下が氷だったせいか、アルトは靴を滑らせた。慌てて支えようとしたルキータにラヴェル、その二人の間にいたクレイルが巻き添えになって、凄まじいスピードで立ったまま滑って行く。
「は……はは、こいつは楽でいいぜ」
何とかバランスを取った四人は立ったまま進んでいくが、不意にはるか後ろから声を掛けられた。
「……どうでもいいがお前ら、状況をよく考えろ」
「え?」
どっこーん!
滑っていた四人が全員壁に激突した。
その足元は、よく見れば氷などないではないか。
なぜ滑ったのやら。
「……まだ騙されているな」
注意深くレヴィンは歩み寄った。
顔に岩の模様を刻み込んだラヴェルだが、めげている場合ではない。
明るいうちに元の集落へ戻るか次の集落へたどり着くかしないと、冬の雪山で凍死しかねない。
顔の模様が消えないまま、洞窟を奥へと進んで行く。
が。
ズガッズザッガシャッ!
「うわーーっ!?」
「きゃーーっ!?」
しばらく進むと、地震もないのに天井の氷柱がふってきた。
巨大な氷の槍だ。危険極まりない。
「これも妖精の仕業?」
「多分な」
「ということは……」
ラヴェルは立ち止まった。
目の前に、厚く氷の張った池がある。
釣り橋は切れ、水中へ沈んでいる。これを渡らないと先へ行けない。
湖面の氷の厚さは充分だ……が……。
「乗った瞬間に、ぱりーん! ってなると思わない?」
「……まあ……そうだろうな」
地面の目一杯の幅が池、周囲は壁面で湖面以外へ回り込むことはできない。
ラヴェルは湖面をたたいてみた。
厚い。
「うーん……でもこれだけ厚ければ割れないよね」
落石にも耐えられそうなほど氷は硬く厚く張っている。
ラヴェル達は恐る恐る池の上に出た。ちょっと進んでみるが、特に何も起こらない。
「うん、大丈夫そうだ」
アルトやルキータ、クレイルも続けて氷の上へ出た。
しかし。
まだ湖面に出てなかったレヴィンが踏み出しかけた足を引っ込めた。
「渡り切るか戻るかしろ!」
「え?」
瞬間、氷の破片が宙に舞った。池の外周に沿ってヒビが入る。
割れるか!?
ラヴェル達は思わず足を止めて身構えたが……何も起こらない。
しかし。
「……ええっ」
やがて足元が傾いた。
ざばぁっ!
次の瞬間、池のふちに沿って盛大な水しぶきを上げながら、池そのものが転覆した。
|
「ああ、風邪のときには熱いお茶……」
クレイルが毛布に包まってお茶をすすっている。
三日ほど、ラヴェル達は次の集落で寝込んでいた。
「それにしても、随分と悪質じゃないか」
レヴィンは彼らの横で靴を磨きながら、宿の主人に話しかけてみた。
「冬を呼ぶだけの存在かと思っていたんだが」
「そうだなぁ……ジャックが悪さをしたなんて聞くのも我々は初めてだしな。ヤツは長い間そこの祠に住んでいるが、姿自体も数回しか見せないし、おとなしいやつだと思っていたんだがね」
そもそも妖精なんていたずらが好きなのだから、これくらいはやってのけるかもしれ
ないが、レヴィンは窓の外を睨みながらつぶやいた。
「……そうか。急にいたずらを始めたとなると、何か理由でもあるのかもな」
「この村では特に変わったことはないよ」
「ふむ……」
全員が元気になると、一行はその祠へと足を向けた。
「これって……」
祠は氷でできていた。
広い空間のど真ん中に氷の柱があり、それがドーム状の壁と天井を支えているらしい。
「……崩してくださいっていわんばかりだよね」
その一本しかない柱の真ん中に、ラヴェルの竪琴が埋まっていた。
ジャックの姿は見えないが、そこらで眺めているだろう。
竪琴を取り出すにはこの柱を崩さなければならなそうだが、柱を崩したが最後、氷の天井が降ってくるのは目に見えている。
「仕方ねぇな、柱を氷で補強するしかないんじゃねえの?」
「そうだね……」
ラヴェルの竪琴は左右対象の美しい曲線を描くリラで、ボディ部にはうっすらと彫金してある。
森の女神エスニャの木々の葉が彫り込まれた竪琴は、飾りとしても美しい。
「もしかして飾ってあるんじゃないかしら?」
「そうかなぁ……」
どのみち、竪琴を取り返さないことにはラヴェルは仕事にならない。
例え下手くそでも。
「じゃぁ……フロスト!」
ラヴェルの扱える五つの基本魔法から、氷の魔法を放って柱を太くする。
レヴィンに魔法を使わせたら、柱を太くする以前に破壊しかねない。
下手な魔法をちまちまと何度もかけてやっと柱は二倍くらいの太さになった。
それをダガーで削って行く。
「ふうぅ〜〜やっと取り返せた〜〜」
最後の仕上げ、竪琴まわりの細かい部分はアルトにまかせ、ようやくラヴェルは竪琴を手に取り戻した。
「あ〜あ、取り返されちゃった」
不意に無邪気な声があたりに響いた。
振り向けば空中に小さな妖精が浮かんでいる。
「綺麗だから飾っておいたのにさ。うん、でもまた取り返せばいいだけのことだし。こうやって」
ジャックが何か唱えると、突然地響きがした。
祠が激しく揺れ、柱や壁に音を立ててヒビが走る。
「ああ!? やっぱりそう来たか〜〜!!」
ラヴェルは竪琴を放り出すと頭を抱えて伏せた。せっかく取り戻した竪琴がすぐに消える。
「やはりな」
「うーん、迫力」
「こんな寒いところで生き埋めはいや〜っ!」
「オレは暖かいところでも嫌だーー!!」
やたらと冷静なレヴィンやまるきり状況を理解していないクレイル、他の三人のあげる悲鳴などにはお構いなし、瓦礫となった雪の塊が大音響をたてて降ってくる。
その大音響の中で、決して大きくはないがよく通る声が確かに響いた。
「……碧氷の盾よ! やめなさいジャック」
|
「え……?」
ラヴェルがハッとして見上た時には、冷たい空気が固まり、一瞬にして氷の巨大な盾となっていた。
その上に轟音を立てながら崩れたドームが降って来るが、頭上の氷の盾はびくともしなかった。
もう何も降って来ないというのに、頭を手でかばいながらラヴェルは辺りを見回した。
その視界の中に、ジャックを抱えた人影がふっと現れた。
細い腕に抱き締められたジャックは竪琴を手にしたまま、じたばたと暴れている。
「は、離してよーー!」
「だ・め・で・すっ!」
まるで子供をしかるように言うとその人影はこちらに近付いてきた。
何故か背後のレヴィンが舌打ちをしたようだったが、ラヴェルはそれは気付かぬふりをした。
「ほらジャック、竪琴をお返ししなさい」
「うーー」
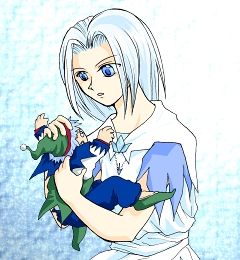
小妖精は不満そうであったが、それでも彼を抱えていた人に睨まれると渋々竪琴をラヴェルに返した。抱えていた人をチラッと上目で見る。
「あーあ、喜んでくれると思ったのにな」
「盗んだものなんか頂いても喜べませんっ!」
「ぷう」
ジャックを捕まえていたのは美しい人であった。男性か女性かは……わからない。
しばらくその人にお説教をされるとジャックは外へ出て行った。ラヴェル達とその美しい人だけが残る。
「……申し訳ありません、よく言って聞かせましたのでどうかお赦しくださいませ」
「え、ええ……取りあえず、返してもらえれば結構です……」
氷のドームの中にふっと姿を現したところを見ると、この人は人間ではないのだろう。
半分警戒しながらラヴェルは尋ねてみることにした。
「ところであなたは?」
「私は……名前というものはございませんので……何と答えればいいでしょうか?」
その人は少し首をかしげ、やがてこう紹介した。
「私は上都より降りて参りました。氷のクリスタルを守らなければならないので、こうして寒いところにおります。クリスタルは上都の城にあったのですが、あいにく城が滅びてしまったので、地上のここなら安全かと思いましたので……」
「???」
言っていることがさっぱりわからない。
しかし連れにはわかったようで、レヴィンはぼそりと呟いた。
「氷……シャングリラのセラフか」
「!」
その美しい人は驚いたようにレヴィンをみつめ……やがて深々と一礼した。
「おっしゃるとおりです。かの至高城から参りました」
「あの……話が見えないんだけど」
間に立っているラヴェルはさっぱりわからない。シャングリラというのは伝説の美しい都のことだが、それがどうかしたのだろうか?
やっと気が付いたように、その美しい人は説明を加えた。
「シャングリラというのはアスの国……あなた方が天空界と呼ぶ島々の更に上に浮かぶ、セラフの都の一つです」
「アスの国……?」
天空界は二層に分かれているという。
人間達の間で伝わっている伝説によれば、天空界とは古代のミドガルドが吹き飛んだものだといわれていた。
しかし、連れの話が真実ならば、その更に上に正真正銘の原初からの天空世界、天津国アスガルドがあるという。
「え? じゃぁ……」
そこから来たのであれば、この目の前の人物は天空人ということになる。
思わずラヴェルは背後をまじまじと見つめた。
「……何だ?」
「う、いや、何でも……」
元どおりに前を見ると、目の前にいるのは翼こそはえていないが、伝説のとおり白くゆったりとした衣に身を包み、姿形も美しい。
後ろの誰かとは大違いだ。
ラヴェルは再び振り向くと、自称天空人を指で突っついた。
「ところでセラフって何?」
「……お前、それでも本当に吟遊詩人か? セラフというのは上都に住む精霊のような存在だ。単体だとセラだな。星の意思を汲み、星や世界を統べる火土風水などの属性を守るのが役目だ。天魔どもに滅ぼされたから全て過去形だがな。この星の全ての存在の中で最も美しい種族ともいわれていた」
確かに、そこにいるセラフらしきものは美しかった。
ベルナール男爵夫人や令嬢、シレジアの王女をどうひいき目に見ても勝てそうにない。
アルトなど、横からルキータに睨まれていることにも気づかずに見とれている。
「しかし、まさか地上で他のセラフを見るとはな」
レヴィンの呟きにそのセラフはゆっくりと頭を下げた。
それにしても……。
「うーん、でもやっぱり天空人ていうと翼が生えているイメージがあるんだけど……」
伝説によると天空人とは魔法に長け、古代からの魔法、禁呪さえも簡単に扱うという。絵画や彫刻では緩やかな白く薄い衣をまとい、背には一対の純白の翼を持った天使にも似た姿で表される、神秘的な種族。
「我々セラフには確かに翼ははえておりますが、それは幽体化している時か、あるいは大きな力を使わなければならない時だけでして、普段の、こうして実体化している時は翼ははやしておりません」
「そうだったんですか」
ほとんどの精霊はただの意識体で、普段は見ることすらできない。それが何かの折には幽体となったり実体となったりして、姿を見せる。
「それよりラヴェル、そろそろ戻らんと、集落につく前に暗くなるぞ」
「え? ああ、そうだね」
「では、ジャックがまたいたずらをするといけませんので、山を降りたところまで同行いたしましょう」
「そうですか……ではお願いします」
竪琴も手に取り戻したことだし、ラヴェルはセラフに軽く会釈すると祠を出た。
|
集落に着いた頃には辺りは薄暗くなっていた。雪も激しく降っている。
「では、人目に付くといけませんので私はこれで失礼いたします」
「はい、ありがとうございました」
集落の入り口でセラフは立ち止まった。礼をするラヴェルに向かって優雅にお辞儀をすると立ち去ろうとし……何か考えてとどまった。
「失礼ですが……」
何故かレヴィンの元へ戻ってくる。
「あなたは……どちらから?」
「やれやれ、聞かれないんで安心していたんだがな」
「差し支えなければ教えて頂けますか」
レヴィンはヒョイと肩を竦めた。
ちらと後ろを見れば、ルキータとアルトはすでに温かい宿に向かって駆けて行き、クレイルものろのろとその後についていっていた。
そこに残っているのはラヴェルだけ。
ラヴェル以外に誰もいないことを確認してから、レヴィンは短く答えた。
「……ザナドゥ。上都ザナドゥだ」
ぷはっと、思わずラヴェルは吹き出した。
ザナドゥといえば伝説に歌われる、永遠の都、至福の土地だ。シャングリラが実存するなら、確かにザナドゥがあってもおかしくない。
「なっ……じゃあレヴィンって本当に天空人だったの!?」
「……それは、今まで疑っていたということだな?」
「だって〜〜……」
能力はともかく、その姿はどう見たって天空人のイメージとかけ離れている。
同意を求めるようにラヴェルはセラフを見、驚いた。
そのセラフが顔をこわ張らせて地面に膝を突いているではないか。
「それは……大変失礼を致しました。どうか、無礼をお赦しくださいませ」
「へ?」
黙って見ているレヴィンの横に並んだラヴェルは間抜けな声を出した。しげしげとセラフとレヴィンを見比べる。
ラヴェルの視線を受けて、またレヴィンは肩を竦めた。
「まぁいいさ、気にすることはない……おいラヴェル、本気で宿に戻らんと凍死するぞ」
「う、うん……」
レヴィンはラヴェルの背を宿の方に向かって押すと、身を硬くしているセラフに声を投げかけた。
「お前もそろそろもどこかへ姿を消した方がいい。少なくともジャックにはその姿を見られているからな。セラフだと知れて妖魔どもに狩られても知らんぞ」
「は、はい……」
先程までの優雅さはどこへやら、セラフはあたふたと雪の中を下がっていった。
そしてふっと姿を消し……その直前、ラヴェルの目には確かに、ほんの一瞬だけだったけれども、美しい一対の翼が映った。
そう、ほんの一瞬だけだったけれども。
つづく
|